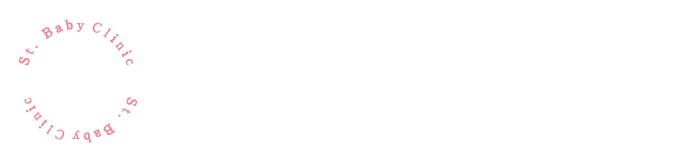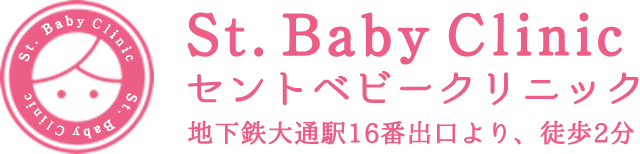トピックス札幌不妊治療クリニックセントベビーからの新着情報や、
トピックスをお届けします。
着床前スクリーニング臨床研究 不妊治療か、命の選別か クローズアップ2015
体外受精でできた受精卵の染色体を幅広く調べる「着床前(ちゃくしょうぜん)スクリーニング」(PGS)について、日本産科婦人科学会(日産婦)理事会が臨床研究の実施を決めた。日産婦は実施の詳細は今後検討すると説明しているが、妊婦の血液で胎児の異常を調べる新型出生前(しゅっせいぜん)診断に続き、倫理的な課題のある臨床研究が始まることに、「命の選別が加速するのではないか」と懸念する声が上がる。臨床研究の実施をきっかけに、不妊治療の一環としての受精卵検査が広がる可能性もある。【下桐実雅子】
◇検査の進歩、背景に
「実施の方向で考えてよいと、理事会の承認を得た。PGSの有用性を検証し、将来の臨床現場への導入を検討する材料にしたい」
日産婦の苛原(いらはら)稔・倫理委員長は先月13日の記者会見で、臨床研究の意義を述べた。PGSの臨床研究では受精卵の全染色体を調べ、染色体の数に異常がないものを子宮に戻す。対象になるのは、体外受精を3回以上しても妊娠しなかった、もしくは2回以上の流産を経験した女性。来年度から3年間かけ、PGSをする女性としない女性各300人ずつを比べ、出産率や流産率などに違いがあるかを調べる。
実施計画は「妊娠年齢の高齢化で、体外受精を繰り返しても成功しない夫婦が増え、対応を迫られている」と臨床研究の必要性を説明する。受精卵の染色体異常は流産や妊娠できない原因になると考えられ、欧米では1990年代から複数の染色体を調べるPGSを実施しているが、効果があるかどうかは分かっていない。このため、日産婦内で「日本でも(PGSを)検証する時期」と実施を求める声が上がっていた。
日産婦によると、体外受精で生まれた子は2012年には約3万8000人、新生児の約27人に1人となった。体外受精をした女性のうち40歳以上の割合は年々増え、10年は35・7%だった。不妊治療専門の「IVFなんばクリニック」(大阪市)の中岡義晴院長は「女性の年齢が高くなると受精卵の異常が増え、時間との闘いになる。実施しなければ分からないが、PGSによって正常な受精卵を早く見つけられれば、妊娠率が高まる可能性はある」と話す。
受精卵の検査には、特定の遺伝子や染色体だけを調べる着床前診断と、全染色体を網羅的に調べるPGSがある。国内では日産婦が98年、一部の重い遺伝病を持つ子の誕生を避ける目的で、着床前診断を認める指針を策定。04年に1例目が承認された。指針が認めるのは着床前診断だけで、それ以外の受精卵の検査は禁じており、PGSは実施できなかった。
だが、受精卵の検査で利用する遺伝子解析技術の進歩が矛盾を生んだ。05年ごろ、高精度で染色体全体の異常を調べられる検査法「アレイCGH」が登場。日産婦は12年、目的とする特定の染色体以外の情報は開示しないことを条件に、着床前診断での使用を認めた。
アレイCGHは、欧米ではPGSに使われている。国内でも一部医療機関が、日産婦の指針に反して、この検査法でPGSを実施するなど、医療現場で着床前診断とPGSの線引きがあいまいになってきた。そこで、日産婦は昨年2月にPGS実施の是非を検討する小委員会を設置。11月には小委員会の報告を踏まえ、倫理委員会が臨床研究の実施を大筋で了承した。
PGSを実施する国内医療機関関係者は9日、「女性は子を産むかどうかを選択できるように、受精卵を選択する自由もある」「受精卵の検査は妊娠の高齢化に伴う染色体の異常をチェックするもので、本来は若いとき産みにくい社会を改善すべきだ」などとする文書を発表した。染色体検査に詳しい臨床遺伝専門医の山本俊至(としゆき)・東京女子医大准教授は、一部で実施が先行している現状も踏まえ、「国内施設におけるPGSの研究計画を学会が主導して統一し、得られたデータを科学的に評価して有効性を判断することは重要だ」と指摘する。
◇ダウン症家族ら 障害への差別、助長懸念 専門家「議論が必要」
13年春、ダウン症など胎児の三つの病気を対象に、妊婦の血液を使って検査する新型出生前診断が始まった。これまでに陽性と判定され、羊水検査で診断が確定した妊婦の97%が中絶を選んだ。
PGSでは、通常22対と性染色体の計46本ある染色体の本数が「1本多い」もしくは「少ない」という過不足を全染色体について調べるため、21番目の染色体が1本多いダウン症や、性染色体が1本少ないターナー症候群などの病気も妊娠前に分かることになる。このため、新たな検査法の拡大に、ダウン症の人や家族からは不安の声が上がる。
日本ダウン症協会広島支部「えんぜるふぃっしゅ」役員、石黒敬子さんには、周囲に支えられながら仕事に就くダウン症の次女(25)がいる。「ダウン症の多くの人が普通の生活をしているのに、生まれる前に選別されないといけないのか。知的障害へ偏見は根強く、さまざまな検査の拡大は、子どもたちの人生に土足で踏み込まれるようで腹立たしく感じる」と明かす。
石黒さんが心配するのは、検査の拡大によって「命の選別」が一般化していくことだ。「多様な生を認めない考え方は、標準から外れた人への想像力を育てず、高齢者にも優しくなくなる。良い社会につながるとは思えない」
また、PGSでは体外受精をしたカップル自身や生まれる子のさまざまな遺伝情報や病気の可能性、子の性別が分かることもあり、情報の取り扱いも課題だ。どのような異常を持つ受精卵を子宮へ戻さないで廃棄するかという基準も決まっていない。柘植あづみ・明治学院大教授(医療人類学)は「この技術は倫理的、社会的問題を多く含む。一つの学会が臨床研究というあいまいな形で進めるべきではない。国レベルでの規制の議論が必要だ」と指摘する。
渡部麻衣子・東京大特任助教(科学技術社会論)は「流産や体外受精の不成功を繰り返すのはつらい経験で、新しい技術に期待する個人の思いは否定できない。一方、それが望ましい出産の姿なのかを振り返る必要もあり、女性たちと接する医療者らが、多様な人が共生する社会を目指す価値を理解しておくことが求められる」と話す。
出典:毎日新聞社