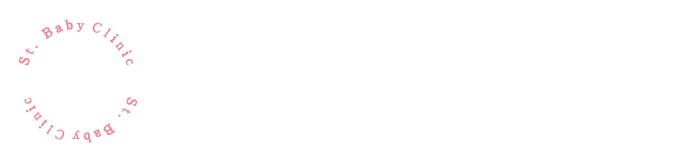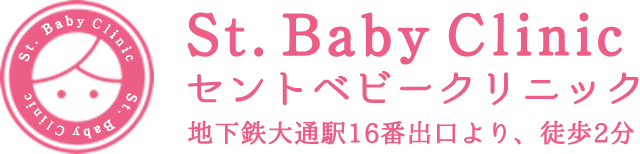トピックス札幌不妊治療クリニックセントベビーからの新着情報や、
トピックスをお届けします。
着床前スクリーニング、異常胚は排除
日本産科婦人科学会(日産婦)は2月7日、都内で開かれた公開シンポジウムで、早ければ来春から日産婦主導で実施を予定している「着床前受精卵遺伝子スクリーニング(PGS)特別臨床研究」の実施計画案を公表した。同案では、受精卵の46染色体の全てを網羅的にアレイCGHで解析し、染色体数が異常のない胚を「適」と判定。その中から移植胚を実施施設が選択して母体に戻し、流産率や出生率などの妊娠予後を改善するかを検証する方針だ。
「命の選別につながる」との懸念の声が上がる中で、同会倫理委員会委員長の苛原稔氏は「原因不明の習慣流産例や反復体外受精(ART)不成功例に対し、疾患治療の観点からPGSの有効性があるのかを臨床研究で検証させていただきたい」と理解を求めるとともに、結果が出た段階で将来実臨床に導入すべきか、倫理面も含めて検討し慎重に進めていくことを約束した。
実施計画案によると、特別臨床試験の対象は(1)体外受精で3回以上不成功例、(2)2回以上の流産を経験した「原因不明習慣流産症例」――に限定し、年齢については現時点では制限を設けていない。実施施設は、体外受精を行うART施設と検査施設に分類。ART施設については、相当数の着床前診断(PGD)を実施している施設の中から学会が指定する方針で、現在6-10施設を想定しているという。また、検査結果の判定については、アレイCGHを用いて全ての染色体を解析後、染色体数に異常がないものが「適」とされ、戻す胚の優先順位は各施設の判断にゆだねられた。
PGS群300症例、コントロール群300症例を目標としたランダム化比較試験を予定しており、期間は3年を想定。1年ごとに中間評価し、状況によっては期間の延長や症例数の見直しなども検討する。具体的な方法は現時点では未定で、研究組織が結成された段階で実務者間で詳細な手順を詰めていくという。
今回のPGS特別臨床試験では、該当症例の流産率の低下や出生率の向上効果の検証を目的としているにも関わらず、染色体数の増減があるものは排除されることになる。この点について実施計画案を説明した同会PGSに関する小委員会委員長の竹下俊之氏(日本医科大学産婦人科学教授)は、「今回はあくまで臨床研究のため、『適』の基準については染色体の数的異常がないものと決めておかなければ、その都度検討が必要になるため、今回はないものと限定した」と説明した。
一方、同小委員の一人、東京都立墨東病院産婦人科部長の久具宏司氏は、PGS導入に対し慎重論を展開した。PGSの進歩により得られる情報の拡張が見込まれる中で、パーフェクトな子を求める「デザイナーベイビー」や男女の産み分けにまで発展する可能性を危惧。さらに、流産リスクが高い女性に限定して行われていたPGSが、「体外受精を受ける女性全てにオプションとして提示されるようになるかもしれない」と、将来的に対象女性が拡大するリスクも指摘した。
また、今回のPGS特別臨床試験に求められるものとして、試験の期間中、かつ対象症例に限って、流産を起こさない異常胚を排除することを明確に宣言する必要があると指摘。その上で、「委員の一人として科学的な有用な結果を得るために、この臨床試験の間だけ異常胚を排除することをお許し願いたいと思う」と述べた。
会場からは、「次世代シーケンサーが控えている中で、卵をどこまで戻すのか、コンセンサスを作りながら実施していかないと歯止めが効かなくなる。研究を始めるのであれば、こうした点をきちんと評価した上で進めてほしい」、「高齢の方がコントロールに割り当てられると時間が過ぎて、結局全て異常胚になってしまうというのは酷ではないか」、「この検査は胚の遺伝学的検査なので、母体側の影響の少ない35歳くらいまでに限定した方が科学的に正しい結果が得られるのではないか」など、臨床試験のあり方に対する意見が続出。
また、昨年12月のPGS特別臨床試験の報道を受けて、問い合わせが殺到している施設の医療者は、ほとんどの人がPGSをやればパーフェクトなベイビーができると勘違いしていると実態を報告した。PGSを実施して異常のない卵を戻しても妊娠しないこともあるため、「臨床研究という形でやるのであれば、対象になる患者が誤解のないカウンセリング体制を取るようお願いしたい」と日産婦に強く求める場面もあった。
今後、日産婦ではこれらの意見を倫理委員会にて精査し、実施計画に反映していくという。
出典:日本産科婦人科学会