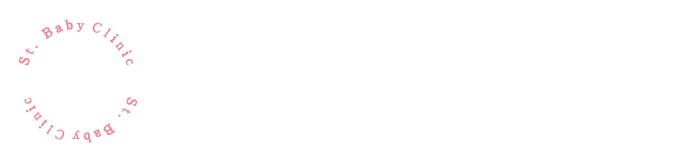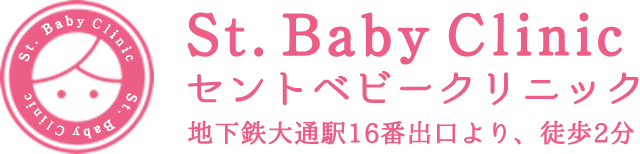トピックス札幌不妊治療クリニックセントベビーからの新着情報や、
トピックスをお届けします。
子どもの保護、優先 代理出産「産んだ女性が母」 法案骨子、自民が了承
第三者がかかわった生殖補助医療で、複雑化する恐れのあった親子関係を規定する法案の概要が固まった。自民党の法務部会・厚生労働部会などの合同会議が26日、民法の特例法案の骨子を了承した。法的な母をめぐってトラブルになりやすい代理出産は、依頼した女性ではなく、産んだ女性を母親と定める。子どもの保護を優先させた形だ。
■海外実施のケースを想定
特例法案は、国内での代理出産を認めるものではないが、海外で行うケースがあるため、民法で明文化されていない親子関係を定めることを目的とする。
骨子では、第三者の卵子を用いた場合、出産した女性をその子の母親とすると規定した。卵子の提供を受けて、子を望む女性が自分で出産するケースでは、この女性の希望に沿うことになる。
子を望む夫婦が受精卵を提供して、妻以外の女性に産んでもらう代理出産では、妻はすぐに母親にはなれず、養子縁組などの手続きが必要となる。自民党の合同会議では今後、代理出産を依頼した夫婦と生まれた赤ちゃんで親子関係が成立できるような制度を検討するという。
早稲田大学の棚村政行教授(家族法)によると、代理出産を認めている米国の一部の州では、子どもが生まれる前に、代理出産する女性との契約内容を裁判所に確認してもらえば、生まれた時に依頼した夫婦の子として認められるという。
東京大の神里彩子特任准教授(生命倫理政策)は「子の福祉を考えれば、産んだ女性を母親とするのは妥当だ。たとえ代理出産の依頼者が引き取りを拒否しても、必ず母親が存在することになる。生まれてきた子が健やかな人生をスタートできるよう、法的な親子関係をあらかじめ決めておくことが大切」と指摘する。
金沢大の日比野由利助教(社会学)は「代理出産を認めるのなら、『産んだ女性が母』は時代遅れ。代理出産を認めている国では、養子縁組を経ずに依頼者を親とする仕組みもある」と語る。
また骨子では、夫以外の男性から精子の提供を受けた場合、その提供に同意した夫は生まれた子を認知しなければいけないとした。
生殖補助医療の法整備を検討している自民党プロジェクトチーム座長の古川俊治参院議員は、民法特例法案を今国会に提出したいと述べた。ただ、生殖補助医療の法制化は国内で代理出産を認めるかをめぐって意見が分かれている。2年かけて国会で議論してもらい、議員立法を目指したいとしている。(福宮智代、合田禄)
出典:朝日新聞