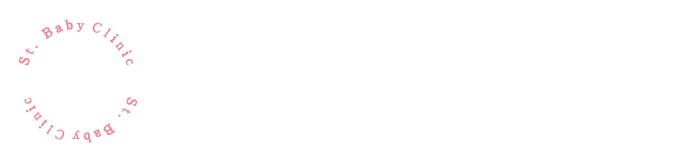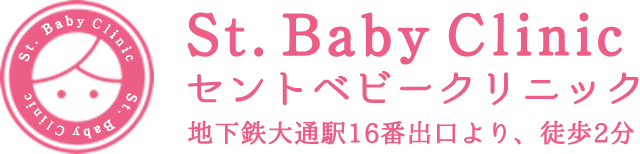トピックス札幌不妊治療クリニックセントベビーからの新着情報や、
トピックスをお届けします。
ゲノム編集「ヒト受精卵の改変は危険」 技術発見者に聞く
遺伝情報を簡単に変えられるゲノム編集技術「CRISPR(クリスパー)/Cas9(キャスナイン)」を発見したエマニュエル・シャルパンティエ博士(47)が9日、朝日新聞のインタビューに応じた。中国のグループがヒト受精卵の遺伝子改変を昨年発表するなど研究の倫理の問題も出ている。「この技術はヒトの生殖細胞で使うべきではない」と語った。
シャルパンティエさんは微生物学や遺伝学が専門で、独マックス・プランク感染生物学研究所ディレクター。学術情報サービス会社トムソン・ロイターは昨年、ノーベル賞の有力候補に挙げた。京都大と稲盛財団主催の京都賞シンポジウムに招かれ、来日した。
CRISPR/Cas9は元々、細菌がウイルス感染から身を守るための仕組み。シャルパンティエさんらが仕組みを解明、ゲノム編集に応用できると2012年に報告した。「11年に基本的な仕組みを解明したとき、ゲノム編集に使えると思った。長期的目標として応用は常に考えていた」と振り返った。
シャルパンティエさんらは遺伝性の病気の治療に生かそうと企業を創設。「(アフリカや中東で多い)鎌状赤血球貧血や(欧米で多い)嚢胞(のうほう)性線維症で研究を進めている」と述べた。
一方、ヒトの生殖細胞の遺伝子も変えられるため、子どもの外見や能力を自在に操作する「デザイナーベビー」につながるとの懸念もある。日本でも内閣府の専門調査会や日本学術会議がゲノム編集のルールについて議論している。
シャルパンティエさんは「(ヒトの生殖細胞への利用は)危険性があり、正当化されない。この技術は病気の治療や予防で使うもので、人間が手を加えて別のものに変容させるために使うものではない」と訴えた。そして「理想を言えば、最大限努力して各国が合意できる規制づくりを進めるべきだ」と語った。
(阿部彰芳、西川迅)
◆キーワード
<ゲノム編集> 細胞内のゲノム(全遺伝情報)の狙った箇所を、文章を書き換えるようにピンポイントで変えられる技術。1996年に最初の技術が登場し、CRISPR/Cas9は「第3世代」。変える箇所を決めるRNA分子と、はさみ役の「Cas9」と呼ばれる酵素を細胞に入れるだけで変えられる、使い勝手のよさから急速に広まった。
出典:朝日新聞